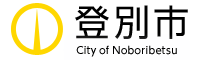公開日 2025年11月20日
ヘルパンギーナとは
発熱とともに、のどに痛みと水疱が現れる「夏かぜ」の一種です
発熱と口腔粘膜に現れる水疱性の発疹を特徴とした急性のウイルス性咽頭炎で、乳幼児を中心に主に夏季に流行する、いわゆる夏かぜの代表的疾患です。
病気の原因となるウイルスは主にコクサッキーウイルスA群ですが、コクサッキーウイルスB群、エコーウイルスが原因となることもあります。
※最新の発生状況については、感染症情報提供サイト(国立健康危機管理研究機構)からご確認ください。
主な症状
2~4日の潜伏期間の後、発熱に続いて咽頭痛が発生し、口腔内に直径1~2mm程度の小水疱が発生します。小水疱が破れた後は浅い潰瘍を形成し、疼痛を伴います。
発熱時に熱性けいれんを伴うことや、口腔内の疼痛のため、不機嫌、拒食、哺乳障害それによる脱水症などを引き起こすことがありますが、ほとんどは予後良好です。
まれに無菌性髄膜炎や急性心筋炎を合併することがあります。
感染経路
感染経路は、主に経口感染、接触感染、飛沫感染です。
急性期には、喉からウイルスが排せつされるため、咳をした時の飛沫により感染します。また急性期から回復期(発症後2~4週間程度)にかけて便からウイルスが排せつされるため、便が付いたおむつや下着などに触れた後は、しっかり手洗いしてください。
治療方法
ヘルパンギーナに特別な治療方法はありません。基本的には軽い症状の病気のため、経過観察を含め症状に応じた治療となります。しかしながら、まれに髄膜炎や心筋炎などが起こる場合があるため、経過観察をしっかりと行い、
・高熱が出る ・発熱が2日以上続く ・嘔吐する ・頭を痛がる ・視線が合わない ・呼びかけに答えない
・呼吸が速くて息苦しそう ・水分が取れずにおしっこがでない ・ぐったりとしている
などの症状がみられた場合は、医療機関への受診をご検討ください。
予防と対策
基本的な感染対策を生活習慣にしましょう
ヘルパンギーナには発病を予防できるワクチンや薬はありません。日頃から手洗い・うがいといった感染対策を生活習慣にすることが大切です。
また、発症後2~4週間頃まで便からウイルスが排せつされるため、発症した乳幼児のおむつ交換を行う時は、排せつ物を適切に処理し、流水と石けんでしっかりと手洗いをしてください。
▶ヘルパンギーナ(厚生労働省)