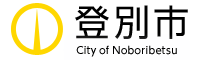公開日 2022年04月22日
国民年金の長い期間中は思いがけないケガ・失業などの理由で国民年金の保険料を支払うことが困難な時があるかもしれません。そんな時は、前年の所得状況に応じて『国民年金保険料全額免除・一部納付(一部免除)制度』がありますので、お早めに相談してください。
「免除申請書」に必要事項を記入して、年金担当、各支所に提出してください。
免除が承認されると
全額免除の場合
老齢基礎年金額を計算する際は、保険料を全額納付した場合の「2分の1(3分の1)」となります。
一部納付(一部免除)の場合
老齢基礎年金額を計算する場合は、保険料を全額納付したときに比べると、次の割合になります。
- 4分の1納付 → 8分の5(2分の1)
- 2分の1納付 → 4分の3(3分の2)
- 4分の3納付 → 8分の7(6分の5)
※()内は、免除期間が平成21年3月以前の割合
ただし、一部保険料を納付しないときは、一部免除が無効となり保険料は未納期間となります。
免除基準
一部納付(一部免除)・全額免除を申請する方のみでなく、申請する方の世帯主、申請者の配偶者の方も免除基準の所得要件を満たしていることが必要となります。
手続きに必要なもの
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
納付猶予制度
同居している世帯主の所得にかかわらず、50歳未満の方で、申請により保険料の納付が猶予される制度です。承認を受けると保険料が後払いできます。
猶予基準
申請者ご本人と配偶者の方も、猶予基準の所得要件を満たしていることが必要となります。
手続に必要なもの
基礎年金番号がわかるもの(年金手帳・基礎年金番号通知書など)
学生納付特例制度
第1号被保険者である、大学、専修学校、専門学校などの学生は、本人の所得が一定以下(各種所得控除後の金額が128万円)であれば申請をして承認を受けると保険料が後払いできます。
追納
免除承認期間及び納付猶予制度・学生納付特例承認期間については、10年以内であれば、さかのぼって納めることができます。
免除申請をしないでいると未納扱いとなり、2年を経過すると納めることが出来なくなります。
年金の各種届出・照会は基礎年金番号で
加入する制度が変わっても同じ基礎年金番号を使用します。
加入に関するすべての手続きや照会は基礎年金番号で行います。
基礎年金番号が記載された「年金手帳」や「基礎年金番号通知書」は一生使用する重要なものです。大切に保管してください。
問い合わせ
保健福祉部 年金・長寿医療グループ(年金担当)
TEL:0143-85-2137
FAX:0143-85-1108
E-Mail:nenkin@city.noboribetsu.lg.jp