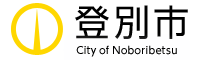公開日 2025年05月22日
国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です
国民健康保険税の納税義務者は、住民票上の世帯主です。世帯主本人が国保に加入していなくても、世帯員が国保に加入している場合は、世帯主が納税義務者となります(これを「擬制世帯主」といいます)。擬制世帯主の所得金額に対して保険税が賦課されることはありませんが、加入者の所得に応じてかかる保険税の軽減割合を判定するときは、擬制世帯主の所得も判定に含まれます。
国民健康保険税の計算
国民健康保険税は、医療給付費分(加入者が病気やけがをした時の医療費を支払うために負担するもの)・後期高齢者支援金等分(75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援するために、74歳以下の方全員が負担するもの)・介護納付金分(40歳以上64歳以下の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料に相当するもの)から成り立っており、次の方法で世帯ごとに計算します。
| 内訳 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金等分 | 介護納付金分 |
| 所得割(A) | 8.4% | 2.7% | 2.1% |
| 均等割(B) | 23,000円 | 7,600円 | 8,700円 |
| 平等割(C) | 25,000円 | 7,300円 | 4,800円 |
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
保険税の計算方法
国民健康保険税(年額)=(1)医療給付費分+(2)後期高齢者支援金等分+(3)介護納付金分
(1)医療給付費分
A 所得割額
…各加入者の令和6年中の所得から43万円を差し引いた金額の合計額 × 8.4%
B 均等割額(人数割額)
…23,000円 × 加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…25,000円
A+B+C=1年間の医療給付費分保険税額(100円未満切り捨て) … (1)
(2)後期高齢者支援金等分
A 所得割額
…各加入者の令和6年中の所得から43万円を差し引いた金額の合計額 × 2.7%
B 均等割額(人数割額)
…7,600円 × 加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…7,300円
A+B+C=1年間の後期高齢者支援金等分保険税額(100円未満切り捨て) … (2)
(3)介護納付金分
A 所得割額
…40歳以上64歳以下の各加入者の令和6年中の所得から43万円を差し引いた金額の合計額 × 2.1%
B 均等割額(人数割額)
…8,700円 × 40歳以上64歳以下の加入者数
C 平等割額(世帯割額)
…4,800円
A+B+C=1年間の介護納付金分保険税額(100円未満切り捨て) … (3)
※年度の途中で40歳になる方は、40歳になる月(誕生日が1日の方は40歳になる月の前月)分から月割計算し、再度納税通知書にてお知らせします。
※年度の途中で65歳になる方は、65歳になる前月(誕生日が1日の方は65歳になる月の前々月)までの分をあらかじめ月割計算しています。
《 ご注意ください 》
- 所得とは、給与所得(給与収入-給与所得控除)、年金所得(年金収入-公的年金等控除)、営業所得(営業収入-必要経費)などの合計で、社会保険料控除や扶養控除等の所得控除前の金額です。
- 土地・建物等の譲渡所得(特別控除後)、株式譲渡所得なども含みます。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険、退職金などは含まれません。
年度の途中で加入・喪失された方の保険税について
年度の途中で国保に加入した方の保険税は届出日にかかわらず、国保に加入した月(会社を退職した日の翌日、市外から転入してきた日などの属する月)まで遡って月割計算します。
また、年度の途中で資格を喪失した方は、国保に加入していた期間分を月割計算します。
低所得世帯に対する保険税の軽減
所得の申告(確定申告、住民税申告、国保簡易申告)がお済みの世帯で、次の表に該当する世帯は、保険税のうち均等割額と平等割額が軽減されます。
| 令和6年中の所得の合計が次の金額の世帯 | 軽減割合 |
| 43万円 + (給与所得者等(※1)の数-1) × 10万円 以下 | 7割 |
| 43万円 + (30.5万円×加入者数) + (給与所得者等(※1)の数-1) × 10万円 以下 | 5割 |
|
43万円 + (56万円×加入者数)+ (給与所得者等(※1)の数-1) ×10万円 以下 |
2割 |
※1.給与所得者等の数とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与の収入金額が55万円を超える方
・公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)または125万円(65歳以上)を超える方
《 ご注意ください 》
- 1月1日時点で65歳以上の方で、年金所得がある場合は、年金所得からさらに15万円差し引いた金額で判定します。
- 専従者給与控除額は、事業所得の必要経費に含めず判定します。
- 専従者給与額は、判定に含めません。
- 土地・建物等の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で判定します。
- 国保加入者ではない世帯主(擬制世帯主)の所得金額も合算して判定します。
後期高齢者医療制度の創設に伴う保険税の軽減
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(以下「旧国保加入者」といいます。)がいる場合は、国民健康保険税がこれまでと大きく変わることがないようにするため、次のとおり緩和措置を行います。
低所得世帯に対する軽減
上記の低所得世帯に対する保険税の軽減については、旧国保加入者の所得と人数を含めて判定します。
平等割額の半額措置
2人世帯で1人が旧国保加入者、もう1人が国保加入者の場合は医療給付費分と後期支援金分の平等割を5年間半額に減額します。また6年目以降も同じ世帯状況の場合は、最大3年間軽減割合を4分の1として減額します。
※該当する世帯の例
夫:75歳(後期高齢者医療制度該当)、妻:70歳(国民健康保険加入)の2人世帯の場合など
子育て世帯に対する保険税の軽減
子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、未就学児の保険税のうち均等割が5割軽減されます。なお、低所得世帯に対する軽減が適用される世帯は、軽減後の額からさらに5割が軽減されます。
| 低所得世帯に対する軽減割合 | 未就学児の軽減割合 |
| 7割 | 8.5割 |
| 5割 | 7.5割 |
| 2割 | 6割 |
| なし | 5割 |
※未就学児とは、令和8年3月31日時点で0~6歳の方です。
非自発的失業者に対する保険税の軽減
倒産やリストラなどの理由で離職して国民健康保険に加入した場合、在職中と同程度の保険料負担に抑えるため、申請により失業時から翌年度末までの間、前年の給与所得を100分の30として保険税を算定します。
※65歳未満の雇用保険による特定受給資格者(倒産、解雇などによる離職)、特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)に限ります。
産前産後期間の保険税の免除
出産する国民健康保険被保険者の産前産後期間相当分に係る所得割額及び均等割額が免除となります。
免除対象期間:出産予定月または出産月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月または出産月の翌々月まで
詳細は、「産前産後期間の国民健康保険税の免除について」をご確認ください。
国民健康保険税の計算シミュレーション
登別市の国民健康保険に加入した場合の令和7年度の保険税額が試算できます。
ご利用にあたっての注意事項
- この試算表による税額は概算ですので、実際の税額と異なる場合があります。
- 国民健康保険税は、世帯主(国民健康保険に加入していない場合も含む)に課税されます。
シミュレーションの対象外となる場合
次に該当する場合は、正確な試算ができませんので、国民健康保険グループにお問い合わせください。
- 年度途中で加入者の増減がある場合
- 世帯主及び加入者に所得不明者(未申告者)がいる場合
- 世帯に後期高齢者医療保険に移行している方がいる場合
- 分離課税所得、専従者給与・控除、純・雑損失の繰越控除がある方がいる場合
- 雇用保険受給資格者(特定受給資格者、特定理由離職者)に対する軽減に該当する方がいる場合
令和7年度登別市国民健康保険税簡易試算表[XLSX:7.24MB]
国民健康保険税の納付方法について
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)の場合
国民健康保険税の納入は便利な口座振替をご利用ください
- 口座振替は、納期限にあわせて指定金融機関の口座から自動的に引き落としになりますので、納期限や納め忘れを気にすることなく、確実に納められます。
- お申し込みは、市役所(各支所含む)の窓口や登別市及び室蘭市内の金融機関の窓口で行えます。
- 手続きに必要なものは、印鑑(通帳の届出印)、預金通帳です。
- 口座振替の開始は、届け出の翌月の納期からとなります。
コンビニエンスストアで納付ができます
皆さんが国民健康保険税を納入しやすいよう、コンビニエンスストア収納を行っています。日中、銀行や郵便局等の金融機関へ納付に行く時間がない方もコンビニエンスストアの営業時間内であれば、土・日曜日、祝日や夜間も納付ができますので、是非ご利用ください。 ただし、「納付書1枚の合計金額が30万円を超える場合」や、「納付書のコンビニ納付用バーコードが汚損または印刷されていない場合」は、コンビニエンスストアでの納付ができませんので、納付書の裏面に記載されている金融機関等で納付してください。
※取扱いコンビニエンスストア(全国の店舗で納付いただけます。)
MMK設置店/くらしハウス/スリーエイト/生活彩家/セイコーマート/セブン-イレブン/タイエー/デイリーヤマザキ/ニューヤマザキデイリーストア/ハマナスクラブ/ファミリーマート/ハセガワストア/ポプラ/ミニストップ/ヤマザキスペシャルパートナーショップ/ヤマザキデイリーストアー/ローソン/ローソンストア100 (50音順)
《 ご注意ください 》
- 納付書は、納期別に1枚ずつです。
- 納付の際は、納付書に記載されている期別と納期限を確認のうえ、間違いのないよう、期別の順に各納期限までに納付してください。
スマートフォン決済アプリによる納付
スマートフォン決済アプリの「PayPay]で納付することができます。
詳細は、市公式ウェブサイト「スマートフォン決済アプリによる納付」をご確認ください。
クレジットカードによる納付
「F-REGI公金支払い」によるクレジットカード納付をすることができます。
詳細は、市公式ウェブサイト「市税及び各種料金のクレジットカード納付について」をご確認ください。
特別徴収(公的年金からの天引き)の場合
特別徴収の対象となる方は、国民健康保険に加入している65歳以上の世帯主で、次の要件を満たす方です。
- 世帯内の国民健康保険加入者が、全員65歳以上74歳以下の方
- 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上あり、国民健康保険税と介護保険料の合計が、対象年金額の2分の1を超えない場合
※年度の途中で世帯主が75歳になる場合や、税額が変更する場合など特別徴収ができない場合があります。
国民健康保険税の納付方法の変更について
特別徴収の対象となっている方でも、申請により納付方法を「口座振替」に切り替えることができます。ただし、滞納がある方は口座振替への変更が認められない場合があります。
また、特別徴収を中止するまでに申請から2~3カ月程度かかりますのでご注意ください。
令和7年度の納期限について
普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)の場合
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 |
|
令和7年 6月30日 |
令和7年 7月31日 |
令和7年 9月1日 |
令和7年 9月30日 |
令和7年 10月31日 |
| 第6期 | 第7期 | 第8期 | 第9期 | 第10期 |
|
令和7年 12月1日 |
令和7年 12月25日 |
令和8年 2月2日 |
令和8年 3月2日 |
令和8年 3月31日 |
※お支払いただいた国民健康保険税は、所得税、住民税の社会保険料控除の対象となります。申告の際には保険税の領収証が必要になりますので、大切に保管してください。
※口座振替の方には、1年間のお支払い額を記載した「口座振替済通知書(申告用)」を1月に送付します。
特別徴収(公的年金からの天引き)の場合
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| それぞれの年金支給日に年金から天引きします | |||||
保険税を滞納すると
災害などの特別な事情がないにもかかわらず、保険税を滞納すると次のような措置がとられる場合があります。
- 督促を受けたり、延滞金が加算されたりする場合、財産の差し押さえを受けることがあります。
- 『特別療養費の支給措置』の対象となり、医療機関の窓口で保険診療分全額(10割)を負担し、後から市の窓口に申請して国保の負担分(7割または8割)の払い戻しを受けることがあります。
- 保険給付を一時差し止めることになり、滞納している保険税を控除して支払をすることがあります。
※納期限までの納付が困難な場合には、早急に国民健康保険グループまでご連絡ください。
国民健康保険税の減免
国民健康保険税は、前年の収入をもとに税額を決定していますが、納税義務者又はその世帯の生計を主として維持する方が次のいずれかに該当することにより生活が著しく困窮し、納入が困難な場合には、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。
- 死亡・心身の重大な障がい、疾病、負傷等により著しく収入が減少したとき
- 事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく収入が減少したとき
- 生活保護を受けたとき
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁等により著しく収入が減少したとき
- その他、これらと同程度の特別の事情がある場合
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード